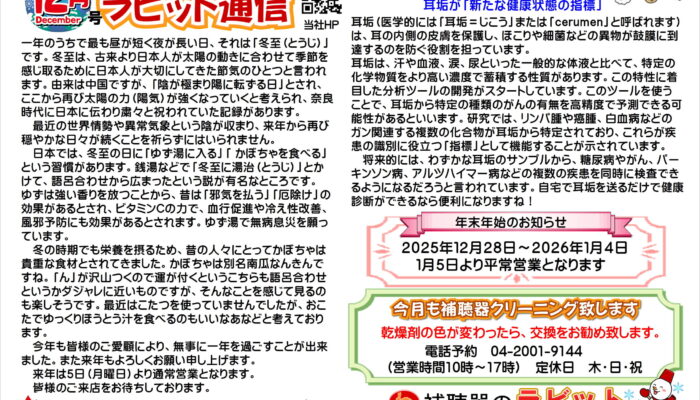ラビット通信 2025年9月号
 2025年9月号
2025年9月号
ランセットというイギリスの医学雑誌をご存じですか?
『ランセット』( The Lancet)は、世界で最もよく知られ、最も評価の高い世界五大医学雑誌の一つとされています。
2024年に発表されたランセット国際委員会の報告は、18〜65歳における難聴が認知症発症の最大の「修正可能リスク因子」であると明らかにし、医学界に大きな衝撃を与えました。 ここでいう「修正可能因子」とは、生活習慣の改善などで対処可能なリスク要因を指します。
「修正可能な認知症のリスク因子14」が発表されました。
2020年の論文3では、①教育水準の低さ、②難聴、③抑うつ、④頭部外傷、⑤運動不足、⑥糖尿病、⑦喫煙、⑧高血圧、⑨肥満、⑩過度のアルコール摂取、⑪社会的孤立、⑫大気汚染の12項目の認知症の修正可能なリスク因子が報告されていました。
そして2024年の論文2では、⑬LDLコレステロール値、⑭視力の低下が加わりました。
難聴は認知症の最大の修正可能リスク因子
「最近、テレビの音が大きくなった」「家族から『聞き返しが多い』と言われる」—こんな経験はありますか?多くの高齢者がこうした症状を単に「年のせい」として放置していますが、実は見過ごせない健康リスクが潜んでいます。
研究によれば、難聴の認知症リスクへの寄与度は7%と算出され、高LDLコレステロール(7%)と同等であり、高血圧(2%)、糖尿病(2%)、喫煙(2%)、肥満(1%)などの他の生活習慣病を大きく上回っています。特に注目すべきは、75歳以上の高齢者の約7割が加齢性難聴に罹患していると推定されている点であり、人口規模から考えても社会的影響が極めて大きいことを示しています。
この国際報告では、難聴を含む14項目のリスク因子を全て排除できれば、認知症発症を最大45%予防できる可能性があると結論づけています。

難聴が認知症リスクを高めるメカニズム
なぜ難聴が認知症リスクを高めるのか、そのメカニズムについては主に三つ挙げられます。
「社会的孤立」聞こえづらくなると、会話の内容を理解するのが難しくなります。「聞き返すのが恥ずかしい」「周囲に迷惑をかけたくない」という気持ちから、次第に人との交流を避けるようになります。集まりへの参加を減らし、外出自体も控えるようになると、脳への刺激が減少し、認知機能の低下を招きかねません。
二つ目は「認知負荷の増大」難聴の方は、会話を理解するために非常に大きな脳の処理能力(認知資源)を使います。常に「聞き取ろう」と脳に負担をかけ続けることで、本来なら記憶や思考に使われるべき脳の資源が枯渇してしまうのです。音は聞こえるのに解らない、これは処理能力が乏しくなってしまう傾向になります。聞こうという気持ちが萎えてしまうと言えます。三つ目は「脳の構造的変化」です。長期間にわたって聴覚への刺激が減少すると、脳の聴覚野が萎縮し始めます。さらに、この変化が脳全体の萎縮や神経回路の変性を促進する可能性があることが、脳画像研究から示唆されています。
音が聞こえないと、脳へ刺激がなくなり脳の処理能力が枯渇してしまうので音が意味をなさなくなります。次第に脳の聴覚野が衰えて小さくなってしまうのです。
年齢とともに進行する聴力の変化
私たちの「聴力」は、20代をピークに徐々に低下していきます。特に加齢性難聴の特徴として挙げられるのが、高音域から聞こえにくくなることです。日常会話で使われる「さ行」「た行」などの子音は比較的高い周波数帯に属するため、これらが聞き取りづらくなると、言葉全体の理解が難しくなります。
例えば、「さしすせそ」が「あしあせお」のように聞こえたり、「かきくけこ」と「たちつてと」の区別がつきにくくなったりします。結果として、「話が見えない」ではなく「話が聞こえない」のに、「見えていないのでは?」と勘違いされることもあります。
注意すべきは、この変化がとても緩やかに進行するため、当人が気づきにくいことです。多くの場合、家族や周囲の人から「最近、聞き返しが多くなった」と指摘されて初めて自覚することがあります。
聞こえの状態に変化を感じることはありませんか。たとえば、最近テレビやラジオの音量を以前より大きくしていたり、騒がしい場所で会話が聞き取りにくかったりすることはないでしょうか。また、電話での会話が聞きづらく、内容がうまく理解できないと感じることや、家族から「同じことを何度も聞き返している」と指摘されるような場面が増えていませんか。こうした状況が続くと、人との会話自体が億劫に感じられることもあるかもしれません。
これらの変化が見られる場合、加齢などに伴う聴力の低下、いわゆる難聴が疑われます。最近はオンラインで聴力をチェックできるツールもあるので、自宅でも簡単に聞こえのセルフチェックが可能です。こうしたツールは、自分の聴力の状態に気づくきっかけとして役立ちますが、あくまで目安にすぎません。正確な診断や適切な対応を受けるためには、耳鼻咽喉科などでの専門的な聴力検査を受けることが重要です。
聞こえの変化に気づいたら、早めに対策を講じることが大切です。補聴器などの適切な対応を行うことで、聞こえの改善だけでなく、認知症リスクを軽減できる可能性があります。認知症リスクの高い参加者だけを解析した研究結果によれば、補聴器を使用した群は、補聴器を利用しなかった対照群よりも、3年後の認知機能低下が約50%抑制されたという報告もあります。
「年のせいだから」とあきらめず、聴力の変化に気づいたら早めに対応することが、認知症予防の第一歩となるかもしれません。ご自身やご家族の聴力について、今一度見つめ直してみてはいかがでしょうか。